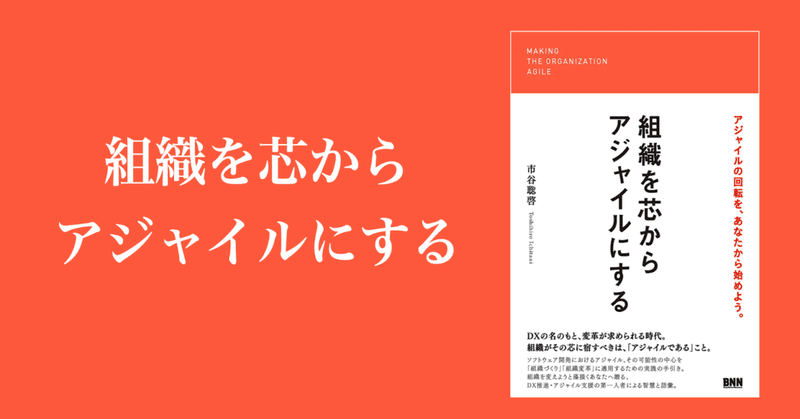
なぜ変化の主語は「組織」になったのか〜「組織を芯からアジャイルにする」に思うこと〜
DXの本丸は「トランスフォーメーション」にあり

市谷聡啓さん(@papanda)の新著「組織を芯からアジャイルにする」が、前著「デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー」から間髪入れずに届けられた。その執筆ベロシティにはただただ驚かされるが、そうまでして市谷さんを突き動かしたものはなんだったのだろうか。
実は、このnoteの主題である「組織を芯からアジャイルにする」にはレビュワーとして参加させてもらっている。改めて、届けられた完成版を読み終えて感じたのは、市谷さんは「デジタル」を冠することで「DXはnot for meのムーブメントだ」と感じている個人、組織をも巻き込み、トランスフォーメーションの回転を広げていく覚悟を決めたのだ、ということだ。
デジタルだがトランスフォーメーションしていない

「デジタルトランスフォーメーション」という言葉が流行し始めたとき、IT企業に所属している人々は「自分には関係ない話だな」と捉えていたのではないだろうか。デジタルを前提としたビジネスを営んでいるのだ、無理もない。
しかし、である。デジタルを前提としたビジネスの意思決定はどのように行われているだろうか。もちろん、データドリブンに、プロダクトレッドに行われている組織もあるだろう。けれども「IT企業」を標榜していてもある種の直感や過去の成功体験ドリブンで意思決定をおこなっている組織もまた、存在している。
もちろん、直感や成功体験に基づく意思決定がよろしくないということではない。むしろ蓄積された経験に裏付けられた直感は強力な武器となる。しかし、デジタルが前提となる以前は喉から手がでるほど欲しかった「顧客がどのようにサービスを利用しているか」というリアルなデータが実際に手中にある今、それをどれだけ活かせているだろう。ただただS3の肥やしになっているのが実態であるならば、それは自分達がトランスフォーメーション前夜に位置していることを示す。
本書が「DX」を冠しなかった理由

これは完全に私の推測になるが、本書のタイトルにあえてDXを冠しなかった理由、そして本文中でもDXに言及する箇所が最低限の分量になっている理由はここにあるのではないか。
DXと冠することで、自分ごとではないと遠ざけてしまう層。けれどもその実、トランスフォーメーションの術を必要としている層。そこにも届けたくて、「デジタル」ではなく「トランスフォーメーション」に焦点を当てたのではないだろうか。少なくとも自分は「デジタル」が全面に置かれていないことで、自分ごととして捉えることができた。
プラクティスこそXPではないが原則と価値観はXPそのもの
2020年に出版された名著、「Clean Agile」。同じく2020年に出版されたMore Effective Agile(こちらも名著!マコネル先生は素晴らしい。)では非常に小さな扱いだったXPが、(Uncle Bobの著書であるから必然ではあるのだが)中心に据えられている。
このClean Agileに深く感じ入っていた自分としては、ソフトウェア開発以外の文脈でアジャイルを語ることにある種の罪悪感さえ感じるようになっていた。そこにきてこの「組織を芯からアジャイルにする」である。サークルオブライフの内側の話はない。それどころか明示的に、対象をソフトウェアの外側へと広げている。ここには「でも、やるんだよ」という覚悟を感じずにはいられなかった。ここにはペアプロもテストファーストの開発もリファクタリングもない。けれどもXPの原則と価値観は確かに息づいている。プラクティスとしてはXPのそれは遠く離れているけれども、本書が目指すところはソーシャルチェンジにほかならない。
様々な組織と向き合ってきたからこそ見えてきた"パタン"
本書には、組織を変革させるための、「芯からアジャイルにする」ためのノウハウがこれでもかと詰まっている。組織を変えていく原動力となる人々はどのようなチームであるべきか、そしてどのように行動していくことが望ましいのかが惜しげもなく言語化されている。
こぼれ話だが、本書で紹介されている「アジャイルCoEの8つのバックログ」が、あまりにも今自分がやっていることと相似していて、レビュー時に椅子から転げ落ちんばかりに驚いたことを覚えている。組織を変えていくための道筋というのは、組織の形はあまたあれど似たような道程をたどるのかもしれない。
長年ひとつの組織に身を置いている自分からすると、自分の経験が普遍的なものなのか自分の組織固有のものなのか全く判断がつかない。なので、本書を読んで、「ああ、これは普遍的なものなんだな」「ここは当てはまらないな、じゃあ自分の現場ならではの何かがあるのかもしれない」などとある種の答え合わせができたのは今自分がいる立ち位置をはっきりさせることに非常に役立った。
なぜ今、組織なのか
2年前に市谷さんが著した「チームジャーニー」は、そのタイトルが示すとおり「チーム」に焦点を置いていた。思い起こせば、2~3年前は「チーム」に対しての関心がずいぶんと高かったように思える。「THE TEAM 5つの法則」などはよく読まれていたし、エンジニアコミュニティDevLOVEでも「チーム」に関するテーマのときは普段よりも参加者が多かった。
さらに遡ると「カイゼン・ジャーニー」では「1人からはじめる」ことが前提に置かれていた。(実は、本書「組織を芯からアジャイルにする」もその原点は同じところにある)
個人から始まり、チームで高まり、組織へと発展していく様は「スクラムマスターウェイ」のそれに似たものがある。
カイゼン・ジャーニーの読者だった層が、その興味関心を個人からチームへ、チームから組織へと広げていった結果としての現在なのか。それとも、もっと大きな社会的なうねりがあるのか。個人的には、後者なのではないかという気がしている。組織を変化させねば立ち向かえないなにかが、今我々の眼前にあるのだ。
あなたのアジャイルはどこから?

「組織を芯からアジャイルにする」ーー。あらためて、刺激的なタイトルだ。
これまでアジャイルを実践してきた人なら「ここでいっているアジャイルとは何か?」「いや、自分のアジャイルとは何か?」が問として浮かび上がってくるだろう。
アジャイルとは縁遠く、組織を変えたいという想いをもってこの書籍と出会った人は「アジャイルってなんだ?」という問が胸に去来するだろう。
その「そもそもこれって何なのよ」を探求することが「アジャイル・ジャーニー」の始まりだ。「前からやってたからこうしている」「アジャイルとはこういうものだからこうする」そうではない心のありかた。なぜそうやるのか?なぜそうあるのか?われわれはなぜここにいるのか?それを問い続ける。答え続ける。変化し続ける。それこそが「芯からアジャイルになっている」ということだ。そう私は思う。
だから、この刺激的な「組織を芯からアジャイルにする」というタイトルを肯定的にとらえているにせよ否定的にとらえているにせよ、どこか心にひっかかっている人にはぜひとも手にとってもらいたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
