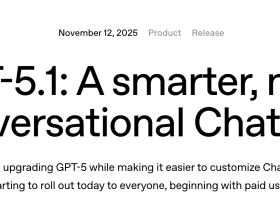11月13日、OpenAIが「GPT-5.1: A smarter, more conversational ChatGPT」を公開した。
この記事では、ChatGPTの中核モデルがGPT-5.1に刷新され、会話性・指示追従性・適応的な思考時間の調整(adaptive reasoning)と、利用者がトーンやスタイルを細かく調整できる新しいパーソナライズ機能を導入した点について詳しく紹介されている。
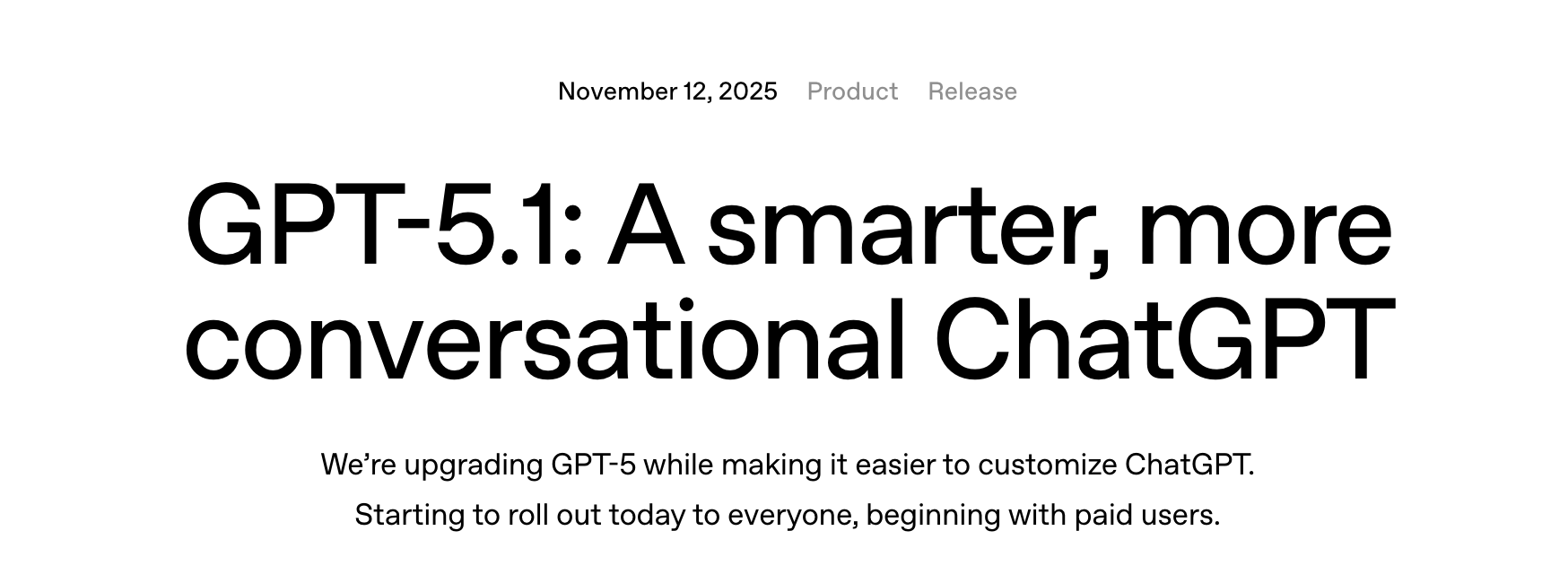
概要
GPT-5シリーズに「Instant」と「Thinking」の2系統でメジャーな改良が入った。Instantは“よりあたたかく会話的”な応答と強化された指示追従性を備え、必要に応じて“考えてから答える”挙動をとるようになった。Thinkingは、問いの難易度に応じて思考時間を精密に配分し、難問ではより徹底した推論、平易な問いには迅速な応答を実現するという。これらは数学・コーディング系ベンチマーク(例:AIME 2025、Codeforces)での指標改善として表れている。
2つのモデル系統の改良点
GPT-5.1 Instant
- 既定の会話トーンが「よりあたたかく、会話的」になり、やり取りの自然さが向上した。
- 指示追従性が改善され、ユーザーが実際に尋ねた質問により忠実に答えるようになった。
- 初めて、難問に直面した際に応答前に思考するかを自律判断する「適応的推論」を採用した。これにより、厳密さを要する場面での正確性が高まる一方、通常は応答速度を保つ設計である。
GPT-5.1 Thinking
- 思考時間の配分がより動的になり、速く答えられる問題では従来比で約2倍速く、難問では約2倍長く思考するなど、タスク分布に応じて最適化する。
- 用語のあいまいさや不要な専門語を減らし、説明の分かりやすさを高めた。職場での複雑な課題整理や技術概念の説明などで取り回しが良くなった。
補足:OpenAIはこの「思考時間の最適化」を、汎用的なチャットタスク分布で比較した場合の相対速度として記述している。標準設定(Standard)での比較だとしている。
モデルの提供形態と移行方針
- GPT-5.1 Autoが各クエリを自動で最適なモデルに振り分けるため、多くの利用者はモデル選択を意識する必要がない設計である。
- 提供開始は有料(Pro/Plus/Go/Business)から順次で、その後に無料・未ログインにも段階的に展開する。Enterprise/Eduは7日間の早期アクセス切替(初期オフ)が用意される。
- レガシー互換として、GPT-5(Instant/Thinking)は有料ユーザー向けに「レガシーモデル」ドロップダウンに3か月間残し、比較や移行期間を確保する。サンセットの方針は今後も十分な予告期間を設けると明記されている。
- APIには今週中に提供予定で、Instantは
gpt-5.1-chat-latest、Thinkingはgpt-5.1として登場し、いずれも適応的推論を備える。
「あなた好みのChatGPT」を実現するパーソナライズ機能
OpenAIは「ChatGPTの口調・文体に対する嗜好は人によって、会話によって変わる」という前提に立ち、ベーススタイルの選択肢を改訂・拡張した。既存のDefault / Friendly(旧Listener)/ Efficient(旧Robot)に加え、Professional / Candid / Quirkyを追加する。さらにCynical(旧Cynic)/ Nerdy(旧Nerd)も存続する。これらの設定はすべてのモデルに適用され、更新は進行中のチャットにも即時反映するようになった。
- 画像(公式ブログ掲載の設定画面)

プリセットに加え、応答の簡潔さ・温度感・絵文字の頻度といった特性を設定画面から直接チューニングできる実験も始まる。会話の流れの中で、ユーザーが特定のトーンを求めた場合にChatGPTが自発的に設定更新を提案する挙動も試験導入されるという。調整はいつでも変更・解除できる。
利用体験上の変化
- 一貫性の向上:パーソナライズ設定やカスタムインストラクションの変更が、開始済みのスレッドにもただちに反映されるようになった。
- 回答の自然さ:GPT-5.1世代全体で、回答はより賢く、自然なトーンに感じられるよう設計されている。
- 安全性情報:安全性への配慮は「system card addendum」で補足され、GPT-5.1におけるアプローチが示されている。
今後の予定と命名規則
今回の更新は「GPT-5世代の範囲内での意味のある改良」を示すためGPT-5.1と命名された。今後も、GPT-5系に対する反復的アップグレードは同様の命名規則を踏襲する方針である。
詳細はGPT-5.1: A smarter, more conversational ChatGPTを参照していただきたい。