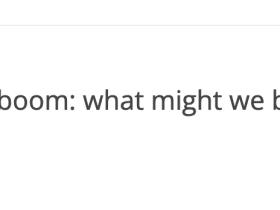10月13日、Rob Bowley氏が「After the AI boom: what might we be left with?」と題した記事を公開した。この記事では、現在のAIブームが終息した場合に何が残るのか、そしてそれが過去のドットコム・バブルとどのように異なるのかについて詳しく論じられている。
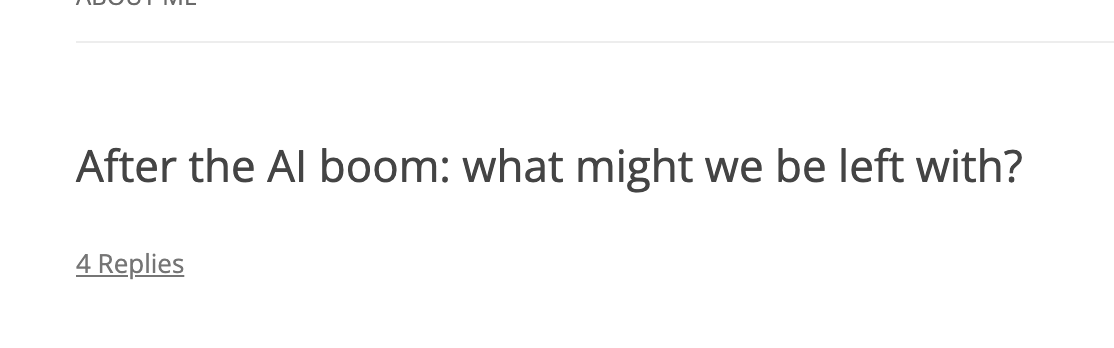
以下に、その内容を紹介する。
ドットコム・バブルとの比較はどこまで有効か
筆者は、AIブームをドットコム・バブルに重ねる見方に一理あるとしながらも、両者には決定的な違いがあると指摘している。
2000年代初頭のドットコム期には、過剰投資によってオープンスタンダードに基づくインターネット基盤(TCP/IPやHTTP、光ファイバーネットワークなど)が整備された。これらは耐用年数が長く、後のブロードバンドやクラウドコンピューティング、現代のWebの礎となった。
当時敷設された光ファイバーの多くは、30年経った現在も通信の主力として稼働しており、端末側の機器を更新するだけで性能を拡張できる。つまり、あのバブルは持続可能なインフラを社会に残したのだ。
一方、今日のAIブームで投資が集中しているのは、閉じられた垂直統合型システムである。
専用化・短命化するAIインフラ
現在のAI関連支出の大半は、NVIDIAやGoogle、Amazonといった少数の大手ベンダーが設計する高価なGPUに向けられている。
これらのGPUは1〜3年程度の寿命しかなく、過酷な運用で摩耗する上、技術進化の速さによりすぐに陳腐化する。しかもそれらは汎用コンピューティング用途ではなく、生成AIモデルの学習・推論に特化した専用チップだ。
これらのチップは、極めて高密度な電力消費と冷却を前提とするAI専用データセンターに組み込まれている。こうした施設は、クラウド初期の汎用サーバー群とは異なり、ハードウェアからソフトウェアまでベンダーの設計思想に強く依存しており、他用途への転用が難しい閉じたエコシステムを形成している。
そのため、もしAIバブルが崩壊した場合、社会に残るのは「短命な専用チップの山と、稼働しない巨大な演算施設(“沈黙したコンピュートの大聖堂”)」かもしれないと筆者は警鐘を鳴らす。
過剰投資がもたらす可能性
とはいえ、筆者は悲観一辺倒ではない。過剰投資が一巡した後に、余剰計算リソースが市場価格を押し下げるというシナリオも考えられるという。
2000年代初頭に通信帯域の過剰供給が起き、結果的に低コストでのインターネット利用が可能になったように、AI計算資源の価格下落は新たな実験や研究を促すかもしれない。
生成AI以外にも、シミュレーション、科学研究、データ解析といった高負荷計算分野での活用が進む可能性がある。中古市場が形成されれば、これまでアクセスできなかった企業や個人にも強力な計算能力が開放されるだろう。
また、AIブームの中で整備された電力網やネットワークインフラは、用途を問わず将来的にも価値を持ち続けると予想される。仮に一部の設備が陳腐化しても、そこで培われた人材・ツール・運用ノウハウは業界全体の資産として残る点は、ドットコム崩壊後と共通している。
「オープンさ」がなければ恩恵は閉じたまま
筆者が最も強調するのは「オープンスタンダードの欠如」である。
インターネットが社会基盤として発展したのは、TCP/IPやHTTPといった誰でも利用可能な標準が存在し、プラットフォームに依存しない普遍的なアクセスを実現したからである。
この「開かれた土台」があったからこそ、過剰な設備投資は最終的に公共財的な価値へと転化した。
しかし、現在のAIエコシステムはその真逆である。計算リソース、モデル、APIはいずれも少数の大企業に囲い込まれた閉じた資産だ。各社が独自のスタックと利用条件を定めるため、ハードウェアが安価になっても、それが自動的に「開かれる」わけではない。
もし共通の標準や相互運用性が確立されなければ、AIインフラの過剰投資は「民間の過剰資産(private surplus)」として閉じたまま終わる危険がある。
筆者は、AIブームがインターネットのような数十年続く社会基盤を残す可能性は低いとしつつも、業界が今からでも構築物をオープン化し共有基盤へ転換する努力を続ければ、将来的に新たな公共的イノベーションの芽を育てられると結論づけている。
詳細はAfter the AI boom: what might we be left with?を参照していただきたい。