本連載は、「エキスパートへの道しるべ(Load to Expert)」をテーマとして、初級者がエキスパートになるためのヒントを、日本を代表するエキスパートの方々に伺う企画です。
本記事では、UXデザイン、ユーザビリティ、アクセシビリティの分野で長年活躍している羽山祥樹さんへのインタビューを通じて、UXの本質や魅力、実践に必要な考え方、学習のコツ、そして注目しているトピックまでを詳しく紹介します。

羽山さんをTechFeed上でフォローしよう!
UXデザインとは何か:ユーザーと向き合う2つの力
――まずは自己紹介と、UXデザインという分野の概要について教えてください。
羽山:羽山祥樹と申します。日本ウェブデザイン株式会社という会社を経営しています。「使いやすいプロダクトをつくる専門家」として、UXデザインや情報設計、アクセシビリティなどに長く携わってきました。
UXデザイン(User Experience Design)やUXリサーチで、私が重視しているのは2つのポイントです。
1つは、ユーザーの心理を深く理解して、本当に嬉しいと思えるプロダクトをつくること。ユーザーに実際に会って、話を聞いて、行動を観察して分析する。そのうえで「どんな心理を抱えていて、何を求めているのか」を明らかにしていくのが、UXデザインの核心です。
もう1つは、その調査・分析プロセスをチーム全体で共有すること。できるだけチームの全員がユーザーに実際に会う経験をするように巻き込んで、プロジェクトに関わる全員が「同じユーザー像」を共有することで、判断がブレずにプロダクトを磨き上げていけるのです。
「ユーザーに会っていない」はUXデザインではない
――UXデザインの範囲は広いですが、「これはUXではない」という明確な線引きもありますか?
羽山:多くのベテランUXデザイナーが共通して挙げるのは、「ユーザーに実際に会わないと、UXデザインとは言えない」という点です。
たとえばアクセス解析ツールで数字を見ても、数字の背景には人間の心理があります。心理はそもそも定量的に表現しきれないものなので、数字からだけでは読み取れません。実際にユーザーと会って観察し、声を聞いて、はじめてユーザーを理解することができます。
羽山さんがUXの道に進んだ理由と出会い
――エキスパートになったきっかけを教えてください。
羽山:私がこの業界に入ったのは1998年。その後2006年に、当時ネットイヤーグループに在籍していた坂本貴史さんという、日本の情報アーキテクチャ分野を牽引していた方とお仕事をご一緒する機会をいただきました。
坂本さんのやっていることを横で見ながら、実際に手を動かしつつ学ぶことで、UXの「考え方」「視点」「型」が自然と身についていったと思います。
2010年には、産業技術大学院大学でUXの専門講座を半年間受講しました。日本のUX研究の第一人者である安藤昌也先生が開講されていたものです。現場で断片的に学んできたものが、この学びで一気に体系化され、個人事業主として働くきっかけにもなりました。
――個人事業主として働くようになってからの気づきなどはありましたか?
羽山:UXデザインの知識だけでは、プロジェクトに貢献しきれないこともあります。
私の場合、営業、プレゼンテーション、プロジェクトマネジメントの経験、エンジニアとしてのスキル、そして経営知識まで幅広く持っていることで、UXデザインを中心とした総合格闘技のようなスキル構成になっています。
UXデザインのスキルを磨くのに加えて、隣接領域のスキルも併せ持つことで、プロジェクトでの役割や影響力が大きくなるのです。
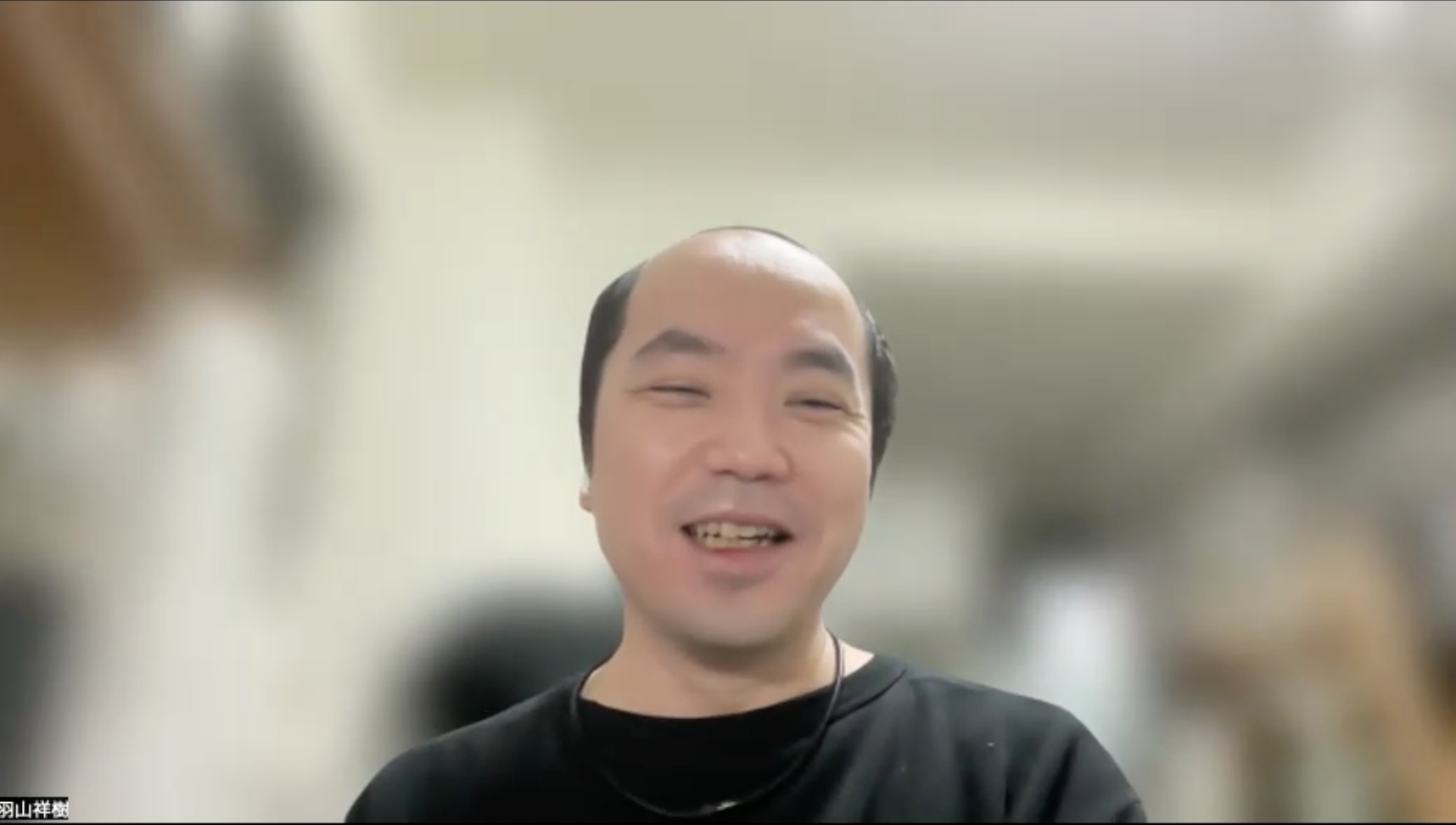
初学者がUXを学ぶにはどうしたらよいか
――これからUXを学びたい人は、どんな方法で学べばよいでしょう?
羽山:最も効果的なのは「業界を代表するエキスパートと一緒に働いて、思考をコピーすること」です。私にとっては坂本貴史さんや安藤昌也先生がそれでした。
エキスパートがどう考え、どう動いているのかを徹底的に真似る。エキスパートの意図と私の考えが異なっても、私の考えはいったんおいて、エキスパートを真似しきる。とにかく「完コピ(完全コピー)」がスキルアップの近道です。
初学者である私と、エキスパートの判断が異なったとき、客観的に考えてエキスパートの判断のほうが正しい可能性が高いと思いませんか?
もし身近にエキスパートがいない場合は、エキスパートがいる場所に行くのが近道です。職場を変える、メンターを探して外部から招くなど、環境を作る努力をすることです。
情報収集の仕方とアウトプットの重要性
――日々の情報収集はどのように行っていますか?
羽山:実務を通して試行錯誤することです。そして、やったことを必ず言語化します。登壇する、noteなどで記事を書く。
自分の体験を言葉にすると、再現性のある知識として蓄積されていきます。逆に、言語化できていない知識は自分の中でも曖昧なまま残ってしまい、再現することができません。
情報を探すときも、J-STAGEやGoogle Scholarを使って一次情報や論文にあたります。
今注目している分野:質的心理学
――現在注目しているトピックはありますか?
羽山:最近注目しているのは「質的心理学」という分野です。UXデザインやUXリサーチでよく使われる手法の多くは、心理学や認知科学にルーツがあります。
中でも質的心理学は、ユーザーの発話や行動を観察し、背景にある心理や動機を掘り下げる方法論が非常に精緻で、ビジネスで行うUX調査よりも一段深い分析が行われています。
学ぶことで、UXリサーチの質が大きく変わると実感しています。注釈:質的心理学とは
※質的心理学(Qualitative Psychology)は、人間の行動や体験、語り(ナラティブ)を深く理解するために、インタビューや観察、ケーススタディなどを通じてデータを言語的・記述的に分析する心理学の一分野。
UXリサーチやユーザーインタビューと親和性が高く、たとえば「ある行動の背景にどんな意味づけや感情があるのか」など、ユーザーの“内面世界”に迫る調査と解釈に用いられる。
羽山さんをTechFeed上でフォローしよう!
初学者へのメッセージ:業界を代表するエキスパートに会いに行け
――最後に、UXを学びたい初学者に向けてメッセージをお願いします。
羽山:「業界を代表するエキスパートのそばで実務をすること」が何よりの近道です。
かつてのTwitterのように、すごい人の発信を追いかけて、懇親会や勉強会で直接会いに行く。足を運んで会ってみてください。
情報を受け取るだけでなく、直接対話し、一緒に働く。これが一番成長速度を高める方法です。
参考リンク集
- 羽山祥樹さん(Xアカウント)
- UXデザインの教科書(安藤昌也 著)
- 産業技術大学院大学
- J-STAGE - 科学技術振興機構の学術論文プラットフォーム
- Google Scholar - 学術論文検索
- 質的心理学研究会(日本質的心理学会)
UXデザインの最先端情報を知りたい方は以下のTechFeedチャンネルをフォローしよう!

TechFeedさんに取材いただきました! 羽山自身がどのようにして "UXデザイン・UXリサーチ" を深めてきたのかを放談しています。
techfeed.io/entries/68a2c8…