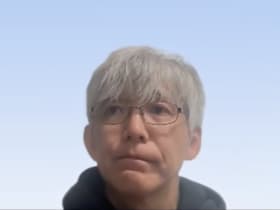本連載は、「 エキスパートへの道しるべ(Load to Expert) 」をテーマとして、初級者がエキスパートになるためのヒントを、日本を代表するエキスパートの方々に伺う企画です。
本記事は、30年以上のIT業界での経験を持ち、現在はTably株式会社の代表を務める及川氏に、プロダクトマネジメントの本質や、初学者が押さえるべき学習法について語っていただきました。
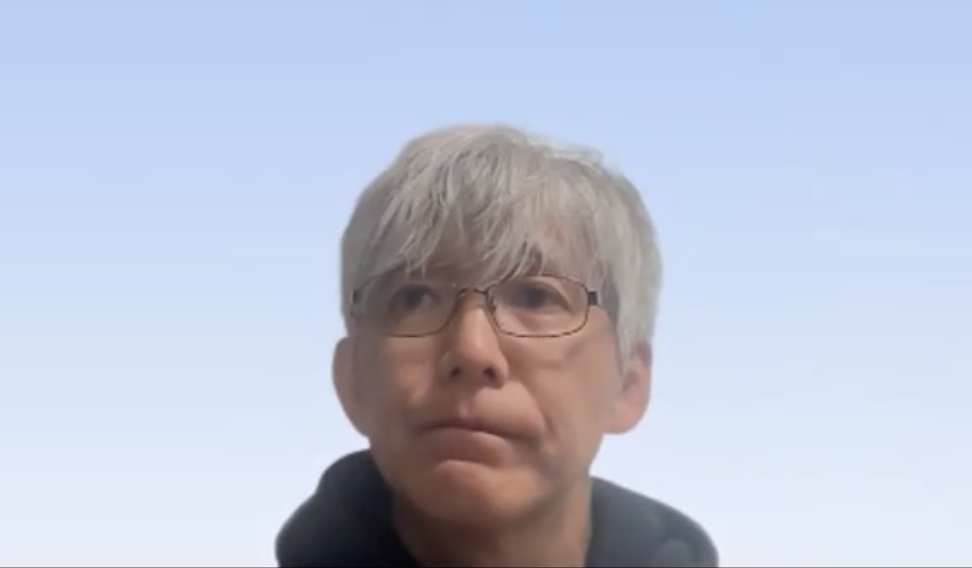
及川さんをTechFeed上でフォローしよう!
プロダクトマネジメントとは何か?その魅力
――プロダクトマネジメントのエキスパートでいらっしゃる及川さんですが、プロダクトマネジメントとは何か、その概要と魅力を教えていただけますか?
及川: プロダクトマネジメントは非常にシンプルに言えば、プロダクトを成功させるための考え方や仕組みです。プロダクトマネージャーはその責任者という存在で、一般的には、技術、UX、ビジネスの3つの要素が必要と言われていますが、各社各様に役割の詳細は異なります。
プロダクトマネジメントの魅力としては、プロダクトを作り、育て、社会を変えていくと同時に、お客様に役に立つ事業を成長させる過程を、積極的にリードできる点だと思います。
プロダクトマネジメントのエキスパートになるまでの道のり
――プロダクトマネジメントのエキスパートになるまでに、どのように学んでこられたのでしょうか?
及川: 基本的には仕事をする中で学んできたので、いわゆる「OJT(On the Job Training)」です。私の場合、「プロダクトマネージャーとは何か」を第三者から教わったことはないんです。見よう見まねで、必要なものを調べて、取り入れながら学んできた感じです。
――少し前には、「プロダクトマネジメント」という言葉自体が知られていなかったようにも思います。
及川: 日本では確かにプロダクトマネージャー、プロダクトマネジメントという認知が始まってから、まだそんなに年月が流れていません。認知が高まったのはここ5年、長く見ても10年くらいではないかと思います。
一方で海外では1980年代から普通に存在していましたね。私が勤めた3社の外資系企業には、すべてプロダクトマネージャーという役割がありました。
――海外ではポジションとして確立されていたのに、及川さんはOJTで学ばれてきたのですね。
及川: そうですね。海外の企業でも座学的に教えている会社もあるようですが、私がいた会社ではそういった研修は存在せず、OJTで周りの先輩から教えてもらったり相談させてもらったりしながら学んでいく形でした。
及川さんが経験してきたプロダクトマネジメント
――及川さんは、実際にはどのようにプロダクトマネジメントをされてきたのでしょうか?
及川: 私の場合はエンジニアリング寄りのプロダクトマネージャーをしていた期間が長かったので、製品のスペックを考えることが多かったです。
ビジネスプランも含む場合もありましたが、私の場合は製品がどう使われるのか、どのような機能であるべきかを考え、それを実現するという役割でした。
私が日本人ということもあり、いかに多様な視点をプロダクトに取り入れるかということを意識していました。
OSやブラウザの開発に携わる中で、国際規格や国際版に貢献することは多かったですね。技術面と事業的価値を両立させながら、日本や東アジアを含む、世界中で必要とされるプロダクトの開発に携われたのは良い経験です。
――プロダクトマネジメントにおける失敗はありましたか?
私の場合は優秀な人に囲まれていたので、会社全体としてそれなりにうまくやってくれる、幸せな環境だったかな、とは思います。
それでも、失敗もたくさんあります。例えば組織を動かしきれず中途半端な製品しか出せなかったり、営業が売れるプロダクトになっていなかったり。マーケティングに失敗したこともあれば、小さな市場に大きく投資してしまったり…なんてこともありました。先程申し上げたように、とにかく実践しながら学んできたので、失敗から得られた知識はとても多いです。
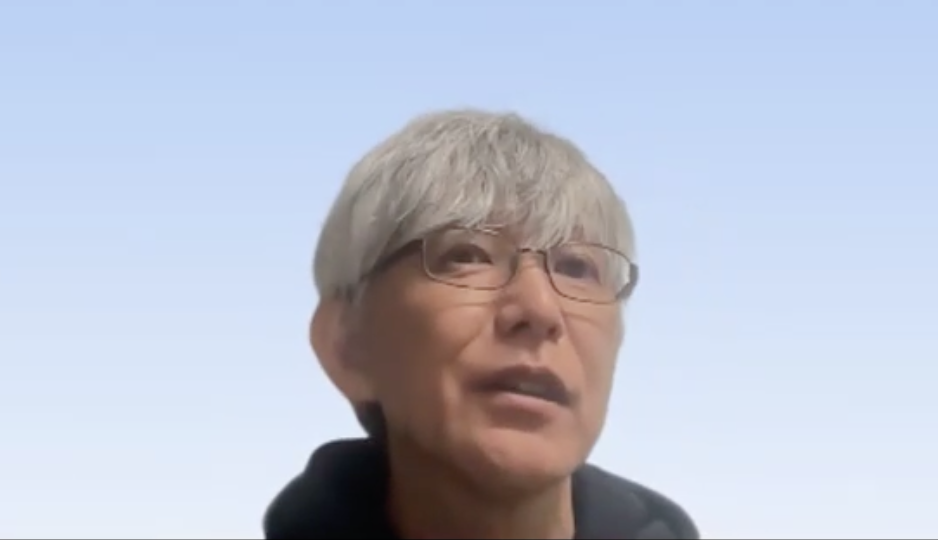
プロダクトマネジメントの学び方
――プロダクトマネージャーを目指す初学者の方におすすめの学習方法があれば教えてください。
及川: まず自分がどうしているかというと、自分でプロジェクトを進めながら、必要と感じたスキルや知識を調べ、取り入れられるものは取り入れるようにしています。
たとえば、ワイヤーフレームを書く必要が出てきたら、書き方を調べます。最近ならFigmaの使い方を調べるといった具合です。本でも公式ドキュメントでも、必要に応じて調べて学びます。
もう一方では、最新情報を知っておくことも重要です。私の場合、The Wall Street Journalのテクノロジーエリアのコンテンツやポッドキャスト、MITテクノロジーレビュー、ハーバードビジネスレビューのテクノロジー関連記事などを読むようにしています。
自分がエキスパートでも学ぶ必要がないとは全く思っていませんし、初学者であってもそうじゃなくても、基本のところは変わらないのではないかと思っています。
――初心者におすすめの学習方法を具体的に教えていただけますか?
及川: 私の会社でもプロダクトマネジメントの研修を行っていますので、それを受けていただくのも一つの方法ですが(笑)、一般的には書籍が良いでしょう。日本語の書籍もたくさんありますし、英語の書籍まで手を伸ばすとさらに選択肢が広がります。
また、YouTubeにもいろんな動画が上がっています。日本語コンテンツも増えていますし、英語コンテンツは膨大な量があります。今は生成AIを使って翻訳や要約もできますから、ざっと見て自分に合うものを見つけると良いんじゃないでしょうか。
及川さんの情報収集方法
――普段の情報収集方法について教えてください。
及川: 先ほど挙げたメディアに加えて、社員が情報を共有してくれることもありますし、支援先の方々から質問されたり情報共有を受けたりすることもあります。
私の場合は、すべての情報を自らアクティブに探すというよりも、信頼できる周りの人からフィルタリングされた情報を受け取るようにしている感じですね。
――見ておくべきサイトやアカウントはありますか?
及川: 技術面では「PublicKey」をよく見ています。比較的色々なベンダーの情報発信が集約されていて、内容も非常にまとまっていると思います。
Xは今はほとんど見ていませんね。プロダクトマネジメントに関して言うと、必要なスキルには普遍的なものが多いので、最新情報を常に追いかける必要があまりないんです。古典的な本やマーケティングの本、戦略論なども十分参考になります。
ただし、最新のテクノロジー(特に生成AI)やUXについては知っておいた方が良いでしょう。プロダクトマネージャーは幅広い領域をカバーする必要があるので、企業内のデザイナーやUXリサーチャー、データサイエンティスト、エンジニアなどとの会話を通じて、最新情報をキャッチアップするのも効率的な方法です。
プロダクトマネージャーは、実は全部を深掘りしすぎない方が良いんです。どの要素をどう組み合わせて価値を生み出すかを理解することが重要なので、重要な情報を広く浅く押さえておくことが求められるかと思います。
及川さんをTechFeed上でフォローしよう!
現在注目しているトピック
――現在注目しているトピックを3つほど教えていただけますか?
及川: 現在注目しているのは、 半導体、自動車、生成AI です。
半導体 については、安全保障上の話題でも注目されており、日本が再び産業を復活させようとしている点が興味深いです。半導体開発の歴史そのものも非常に面白いですし、半導体製造技術は技術の粋が詰まっているものでもあるので、そこもふまえた上で各社の経営戦略なども合わせて見ていくと、プロダクトマネジメントの参考にもなります。
自動車 は日本の製造業の中で最先端、かつ最後の砦のような産業です。業界で「百年に一度の変革期」と言われる中で、技術も大きく変わり、それに伴って業界の勢力図も大きく変わる可能性があり、そこに面白さを感じています。日本人として、めちゃくちゃ裾野が大きい産業でもあるので、そこでお手伝いしたいなとか、するかなっていうところもあって、ちゃんと勉強しておきたいというところもあります。
生成AI は完全なゲームチェンジャーです。とんでもなく大きな変化をもたらすと思います。次々と出てくる技術を試し続けないと、従来のやり方があっという間に陳腐化してしまうので、しっかりと学ぶ必要があります。
プロダクトマネジメント初学者へのメッセージ
――最後に、プロダクトマネジメントを学ぼうとしている初学者の方へメッセージをお願いします。
及川: プロダクトマネジメントでは、 常に学び続ける姿勢が大切 です。単に情報を集めるだけでなく、自分で考えて「こういう情報が必要ではないか」「このスキルとこのスキルを組み合わせるといいのではないか」といった思考が重要です。
組み合わせの妙を常に考え、自分は何を学ぶことで担当しているプロダクトにプラスになるかを考え続けることが大切だと思います。常に好奇心を絶やさず、プロダクトづくりを楽しんでください!
プロダクトマネジメントの最先端情報を知りたい方は以下のTechFeedチャンネルをフォローしよう!